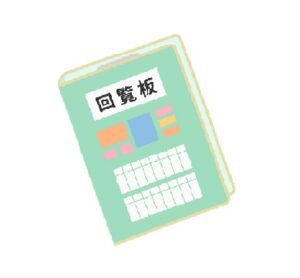竹害対策について

全国各地で問題となっている竹害ですが、当地区でも深刻です。
最近、新・区有地の西端の里道に巨木が倒れていました。数年前も巨木が倒れ長い間里道を塞いでいたこともあります。更に上を見上げるとこれからまだ倒木が懸念される木が何本もあります。いずれもふもとからの竹藪の浸食で山肌の保水力が弱まったこと等が影響していると思われます。


ふもとの竹藪は数年前に一通り伐採しました。しかし、それを撲滅するまでには最低7年はかかると言われ、途中で努力を止めると元の木阿弥になりかねません。やはり事の重大性を踏まえ粘り強く取り組むしかなさそうです。



この問題については、ウェブ上でも当然たくさん取り上げられており、一例をあげておきます。詳しくは、林野庁のHPやウィキペディア等も参照して下さい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
それは、竹の繁殖力が非常に強く、広葉樹林をじわじわと浸食するという事実です。山は本来、ブナやナラ、クヌギといった広葉樹が深く根を張ることで山全体を守り、また良質なミネラルを含む水が蓄えられます。竹には栄養が少なく、竹自身の中に水を貯めるのだとか。竹の根はせいぜい50cmくらいの表層にしか地下茎を張らないため、山の保水力が低下します。
そして竹がぐんぐん成長することで、太陽光が周囲の雑木に届かなくなり、枯らしてしまいます。こうして雑木林は、竹藪に変わっていくのです。里山全体の植生が変わるだけでなく、根の浅い竹の地下茎によって地盤が弱くなることで、土砂崩れなどのリスクが発生するのだそう。
また、人里近い放置竹林がイノシシなど野生動物の住処になると、畑が荒らされてしまいます。例えば熊本県での農業被害は、年間5億円以上にもなるのだとか(令和元年度 野生鳥獣による農作物被害調査結果より)。こうした農業被害は、あまり知られていないかもしれません。
そして、耕作放棄地が地理的条件に恵まれないことが多いのと同じように、放置竹林は急斜面や軽トラックで入れないなどの場所にあることが多く、管理をするのに肉体的な負担がかかるという現実もあります。
竹を枯らすには、タケノコを含め、毎年全ての竹を伐採するという連年皆伐(全伐)式が昔から行われていますが、枯れるまでに早くても数年かかり、何年も続けなくてはいけないこと、そして全てを枯らせる前に中断すると、数年もすればまた竹林に戻ってしまうことから、かなり重労働であるといえそうです。(『バンブーロール』のHPより、なお、本サイトでも当地区の取り組みを載せています。ここ をクリックして下さい。)