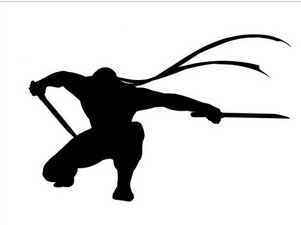

山脈で隔てられた山の国が海の国の一部となったのは?
大和から伊勢へ
伊賀は、律令制が変質し荘園支配が進行するなかで、南東部(=神宮の供給源)以外は、東大寺や興福寺等どちらかというと大和の勢力圏にありました。しかし、有名な黒田の悪党の反乱などもあり、荘園が弱体化し武士が台頭する世になると、京南や伊勢の守護らが伊賀4郡の分割統治に乗り出しました。
しかし、戦国時代を通してその統治はずっと名目的なもので、伊賀はそれらの支配に服することはありませんでした。守護の仁木氏を信楽に放逐したのちは、多くの有力土豪が割拠する、実質上独立共和国のような世界(伊賀惣国一揆)であったとされています。伊賀忍者が発達したのもこの時期です。
この状態に終止符を打とうとしたのが、信長の次男、北畠(織田)信雄(のぶかつ)です。北畠の養子となり同家を乗っ取った後、伊賀を屈服させるための侵攻を敢行しました。これを手引きしたのは下比奈地の下山甲斐守であったとされています。天正伊賀の乱(第1次、1579年)と知られるこの戦いで、伊賀の郷土衆は、丸山城を焼き討ちするなど徹底的に反撃し、信雄軍を惨敗、敗走させました。
2年後の第2次天正伊賀の乱(1581年)で、織田軍は4万を超える軍を6方から投入し、伊賀全土を焼土と化す作戦を展開しました。名張の柏原城が最後の決戦の舞台となり、中世的な世界は終焉しました。そして、強固な縦の支配をめざす封建社会に入ります。
「天正伊賀の乱」については本ウェブサイト(YouTube)の都はるみ『天正伊賀の乱』、『天正乱れ太鼓』もご鑑賞ください。
織豊政権の崩壊から徳川政権~現代へ
天正の乱から1年もしないうちに本能寺の変となり、その後豊臣、徳川、明治維新と大きな政権の変転がありました。徳川政権下では伊賀と伊勢は別々の藩でしたが、ともに藤堂家が管轄するなど行政の基本的な枠組みは維持されたようです。
生き続ける独自文化
明治の廃藩置県で伊賀は三重県に編入されました。しかし、どちらかというと海岸沿いに広がる県の他の市町と、伊賀は風土が大分異なります。行政区分は東海かもしれませんが、言語や文化、生活、交通はむしろ関西圏と言えます。そうした環境の下で、独特の生活や文化、言語、慣習などが育まれ、生き続けてきましたが、それは当然のことと言えます。
